・AI時代で人間に残る価値について
AIが急速に進化する中、「このままじゃ人間の仕事がなくなるのでは?」と不安を感じている人も多いのではないでしょうか。
では実際に、AIが人間の仕事の多くを担うようになった未来、私たちはどうやって稼ぎ、生きていけばいいのでしょう?
この記事では、そんな未来社会において価値を発揮し、稼ぎ続けることができる人間の特徴を、具体的な例とともに解説します。
目次
AIにできること、できないこと
まず押さえておきたいのは、AIが得意なのは「効率化」と「パターン化」された仕事です。
つまり、ルールに従って処理するような業務はどんどん自動化されていきます。
その一方で、人間にしかできないこと、それが今後の「価値」となっていきます。
これからの時代、稼げる人の5タイプ
1. 感性・感情を扱える人(センスがある人)
AIにはまだ難しい「感情の機微」や「なんかイイよね」という感覚を言語化・表現できる人。
例: 坂本龍一、村上隆、NIGO®︎
目指すには:
- 日常で「なんでこれが好きなんだろう?」を言語化
- 自分の好きなモノの歴史や文脈を深掘る
- コピーと再構築を繰り返して自分のセンスを育てる
2.人と人をつなげられる人(コミュニティビルダー)
テクノロジーが進んでも、人と人との「つながり」は希少な価値。
例: 家入一真(CAMPFIRE)、堀潤、ひろゆき
目指すには:
- 小さな場を作ってみる(オンライン・オフライン問わず)
- 人と人を紹介する癖をつける
- 空気を読む力、共感力を育てる
3.意味やストーリーを作れる人(ブランドディレクター)
単なる商品ではなく、「なぜそれを作るのか」「どんな世界観があるのか」を形にできる人。
例: 佐藤可士和、田中泰延、中川政七商店の13代目
目指すには:
- 普段から「これはどんな意図で作られてる?」と考える
- コピーライティングや心理学を学ぶ
- ブランド事例をケーススタディ的に研究する
4.自己表現ができる人(アーティスト・思想家)
自分の価値観や想いを、誰かに届けられる力を持つ人。
「量産されない個性」が武器になる。
例: 庵野秀明、マツコ・デラックス、ZINE作家など
目指すには:
- 自分の内面や違和感を言語化する習慣
- 形にする(ブログ・動画・絵・音楽など何でもOK)
- まず1人に刺さるアウトプットを意識
5.AIに使われず、AIを使う人(テクノロジーを操る人)
AIという道具を使いこなして、新しい価値を生み出す立場にいる人。
例: 松尾豊(東大AI研究者)、イーロン・マスク、AIクリエイター
目指すには:
- AIツールを日常的に使う(ChatGPTや画像生成など)
- プロンプト力(命令の工夫)を磨く
- 技術よりも「何に使うか」を考え続ける
正解を探す時代から、「問い」を持つ時代へ
AIがあらゆる作業をこなすようになった時、人間に残るのは「何をしたいか」「どう生きたいか」という問い。
これから大切になるのは、情報の処理能力ではなく、自分の感性や価値観を持って、それを表現し続ける力です。
まとめ:稼げる未来人になるためのヒント
- 好奇心を持ち続ける
- 表現する習慣をつける
- コミュニティを大切にする
- AIと遊ぶように付き合う
- 「正解」より「おもしろいか?」を大事にする
仕事が変わっても、「人間にしかできないこと」はきっと残る。
そして、それこそが次の稼ぐ力になる。
最後に
ここまで読んでくださりありがとうございます。
実はこの文章はChatGPTに書いてもらった文章です。アイキャッチの画像もChatGPTに作ってもらいました。
AIを使えばこのようなブログ記事も数秒で書くことができちゃうんです。しかも納得感がある内容ですよね。
正解を出すだけのブログ記事にはもう価値はないのかもしれません。AIの知能指数が人間のはるか上を行ったとき正確な答えを出せるのはAIです。
AIが言うように、自分はどう生きたいのか?何をしたいのか?という問いをもつ。その答えが自分だけが持つ価値観です。個性です。
どう生きたいのか?何をしたいのか?が決まれば、あとはAIを上手に使って実現させていけばいいのではないかと思います。
私自身ChatGPTを使ってみてブログ記事の内容も改めようと思いました。
誰に何を伝えたいのかどんな価値を提供したいのか…考えさせられました。
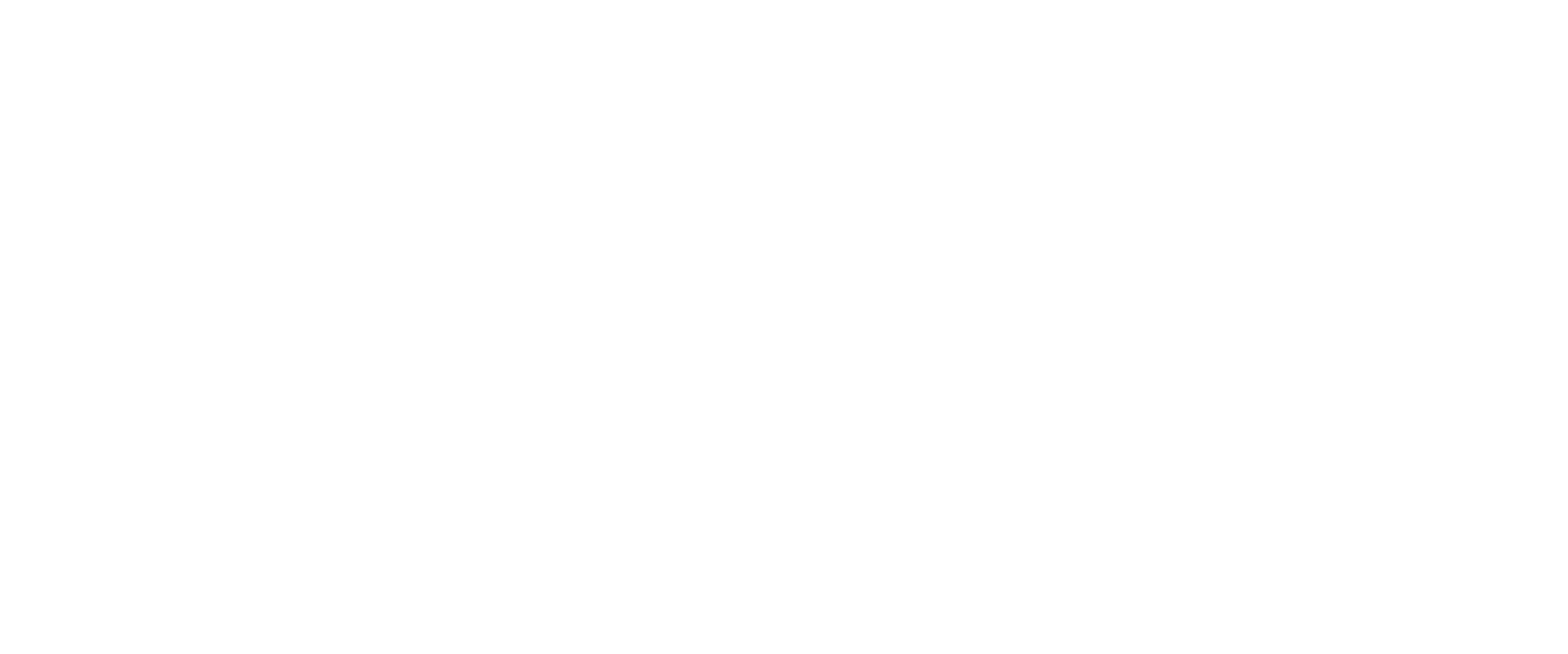
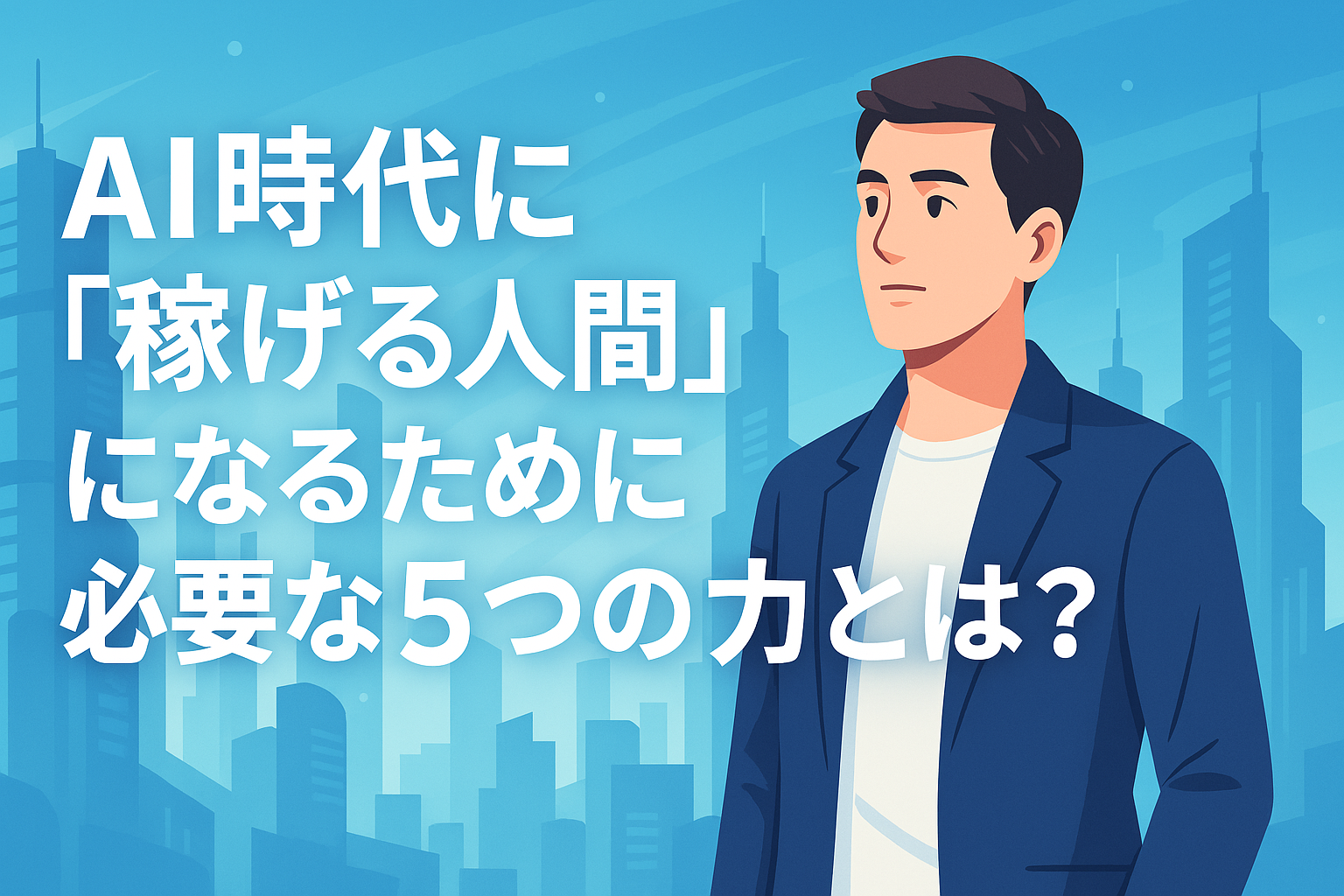

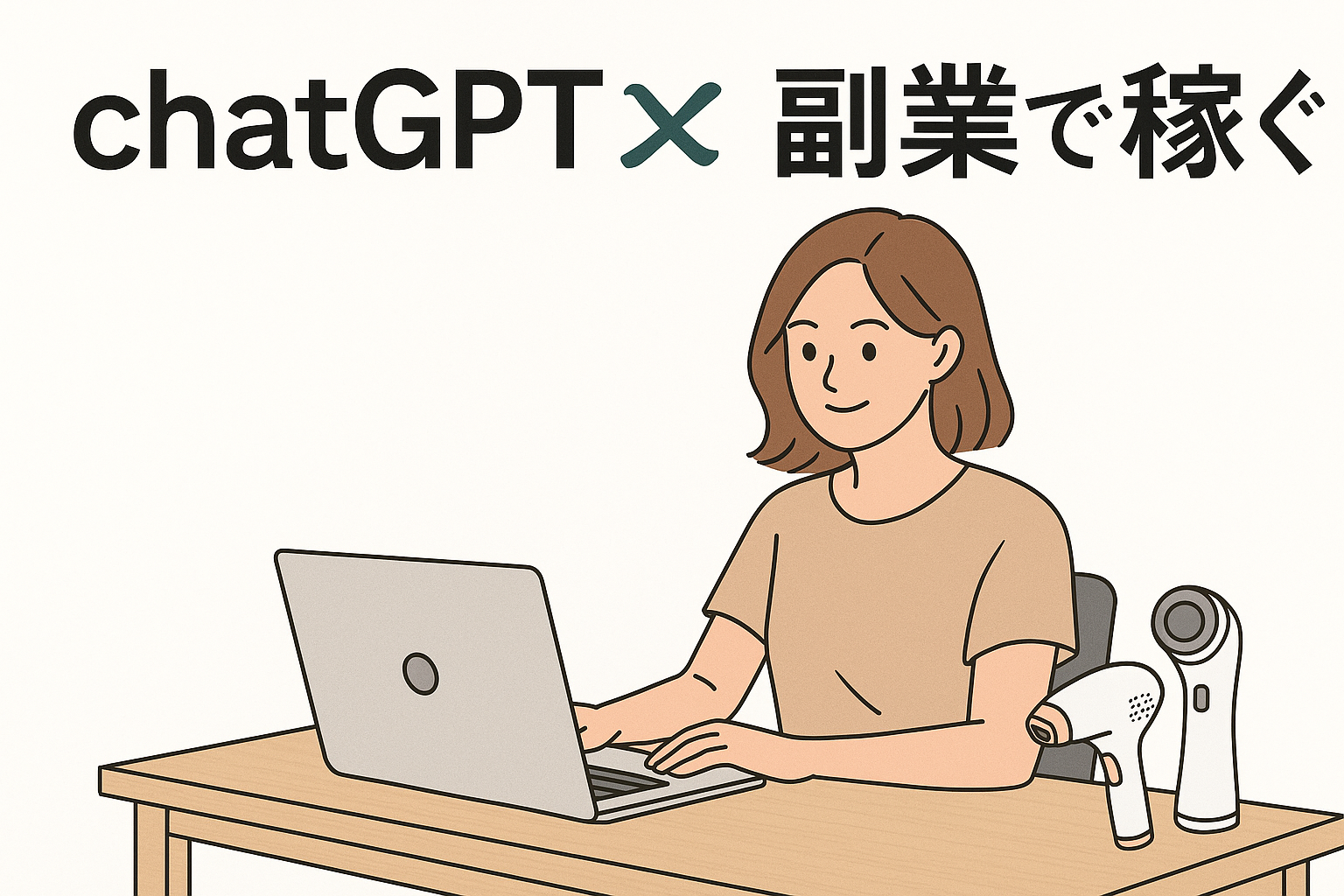
コメント